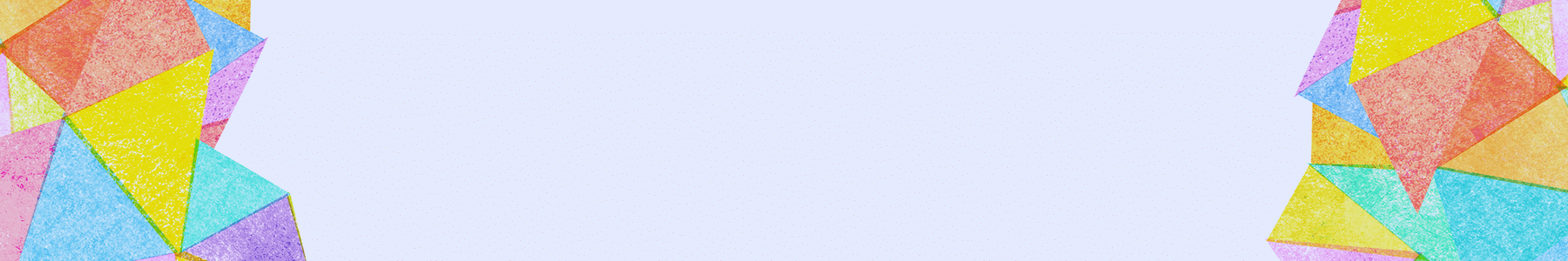黒板の前に立つ先生、前を向いて座る子どもたち。
ベルが鳴れば一斉に起立し、「起立、礼、着席」。
ノートにびっしりと写された板書──。
…その光景、30年前と変わっていません。
子どもや保護者のリアルな声
「もっと自由に学びたい」
「授業がつまらない」
「学校は我慢する場所になってしまっている」
これは、私が現場や相談で耳にしてきた、本当の声です。
なぜ変わらないのか?
実はこの背景には、日本特有の歴史・制度・文化が深く関係しています。
戦後の教育制度の成り立ち、評価の仕組み、社会の価値観──。
それらが何十年もかけて、教室の形や学び方を固定化してきました。
世界では、すでに変化が始まっている
フィンランドの総合学習。
ニュージーランドの探究カリキュラム。
シンガポールの自己主導型学習。
子どもたちが「自分で学びをデザインする」国は、確実に増えています。
今の日本の教育はなぜ変わらないのか?
そして、変えていくために、私たちに何ができるのか?
世界の最新事例から、日本でできる第一歩、
そして実行後に見える未来まで──。
詳しくはこちらで解説しています。
👉 noteで読む